〜課題解決を実現できるか〜
9. DRPというスキーム
そのような中で、2000年前後あたりからDRP(ダイレクト・リペア・プログラム = Direct Repair Program)というスキーム(仕組み)が損害保険会社によって車体整備業界に導入されてきた。これはもともと、日米貿易摩擦による不均衡是正という課題解決のため市場開放を迫られた保険市場に、アメリカや欧州に本拠地を置く外資系損保会社が相次いで日本に参入したからだ。その際に、損保会社が本国で採用していた手法を日本に導入したのである。参入した損保各社は、ともに保険代理店を持たない通信販売を利用した販売方法ゆえ、保険会社が修理工場への入庫誘導をコントロールする体制で、それぞれの指定工場ネットワークを構築した。それが業界に今も大きな影響を与えている。
国内生保系や通販系の損保会社も後を追って相次いで参入してきた。新規参入した各社は、顧客に向けて販売から修理を担当するエリアで、それぞれの基準に見合う修理工場を「指定工場」として認定した。地域別に工場をランク分けして選定し、その工場に優先的に作業を依頼する手法のことをDRPと称していた。そしてそのスキームが業界に徐々に定着していった。指定工場を選定する上では、工場にあるボディフレーム修正機、塗装ブース、見積りシステム、スタッフ数、代車保有台数などのデータを収集し、それぞれ独自で数多くの条件を設定した。
さらにDRPの流れは、顧客から事故が発生した連絡をコールセンターが受け、損保会社自らが周辺の指定工場を探して手配を依頼する。緊急の場合、現場急行するために24時間体制でのロードサービスを提供(自社でも提携でも可)し、工場の負担による無料代車提供などのサービスを手配する。また、見積りの際、画像伝送などで確認、コンピュータ見積りシステムで作業内容の確認と金額チェック、価格協定、修理完了になれば、修理費の見積り金額の工賃からレスカウントした10%が工場の手数料になるなど、一定の条件を設けている。一方、国内損保会社や共済では公に指定工場として明かしていないものの、独自に工場の評価リストを持っており、通販系損害保険会社と同様に入庫を紹介する仕組みを構築している。
そのため、各地域で評価の高い車体整備工場には、一社だけでなく数社の保険会社や共済から指定工場の認定を受けることになり、一軒のショップに集中して看板がつけられ、修理依頼が数多く連絡を受けるという結果に至っている。
カーディーラーの下請けにはレスカウントがあることは前章で記したが、損保会社・共済の指定工場になれば、工賃の10%レス、自社で見積り書作成、部品発注を手配できることなどをメリットと考える工場も多い。ディーラーや損保会社。こうした元請け先からの誘導による支援がなければ、車体整備という業種は成り立たなくなっているのが事実である。
つまり、結果としてこうした下請け構造からなかなか脱却できないのが車体整備業界の宿命といえる。
10. 評価基準と設備投資
🟠車体整備の指定工場選定の条件
損保会社・共済の指定工場に選定されるための資格要件は、導入されている設備や人員によるところが大きい。
イギリスには、損害保険会社の研修機関であるサッチャムが定めたBS10125というボディショップ向けのスタンダードがあり、それを取得することが一定の基準となっている。
日本では国の機関としては、車体整備工場のランク分けや格付けのような要件や技術水準を設定していない。そのため各社は、その時々に必要な自主的に基準を設定し、優れた機器を備えていれば良い作業品質になることを前提として、指定工場各社が選定した機器を評価する方法をとっている。最近の傾向としては下記の通りである。
自動車はその都度、次から次へと新車に新技術が搭載されるため、車体整備作業において常に対応を迫られる運命にある。そのためボディショップは、新技術をクリヤーするための技術を習得しなければならない。
鈑金作業では、骨格を修正するための精度の高いボディフレーム修正機が代表的な機械設備であるる。ジグ式、ベンチ式、台上式、床式などがあるが、タイプは問わない。引っ張り強度の高い高張力鋼板の外板パネルでの修復作業で使用するためのスポット溶接機、スポット溶接されていたパネルを剥がして、新たにそこに新品のパネルを補修するため、穴を埋めるために半自動ミグ溶接機と技術などが要件となっている。さらに、これまでに述べたADAS搭載車両などではボディや骨格にズレがないかが条件となるだけに、より安全への対応が重要になり、3次元計測器なども必要になっている。
塗装作業では、上下圧送タイプの塗装ブース、CO2排出対策の環境保護に対応した水性塗料など、非常に高額な設備投資が必要になる。VOC(揮発性有機化合物)に関しては厳しい環境規制が日本にはないが、少しずつ厳しくなっている。
欧米では、環境に考慮したVOC規制があり、補修塗料でも当たり前のように水性塗料を採用している。一方日本では、カーメーカーの新車ライン塗装は水性塗料が採用されているが、いまだ補修用水性塗料の普及度は低調である。輸入車ディーラーではほぼ採用しているが、ようやく国産メーカーのディーラー工場で採用が増えているようだが、まだ努力目標という段階である。
鈑金塗装の技術以外にも、フロントにおける接客対応や、トラブルが発生した際現場に急行するロードサービスでの現地対応、さらにはASVやEVへの対応など、評価される条件はさらに加わっている。
🔴指定工場になるメリットは
こうした損害保険会社や共済の指定工場になることによって、修理工場にとっては入庫確保と経営の安定につながると考え、積極的に設備投資に力入れるボディショップが増えてきたのが2000年以降の潮流といえる。そして、自動車が高度化したこともあり、需要も多くなり業界も活性化してきた。
高い技術力を発揮する機器を導入することは、客観的な評価を受けることであった。それと同時に、地域の顧客に選ばれる工場だと評価を受けているからだ。それだけ顧客からの信頼を勝ち取ってきた証左だ。

そして近年は、車体整備業界では第三者認証機関による審査を受けているショップが増えている。国際的な品質保証プログラムであるISO9000を取得したり、ドイツに本部のあるTÜV(テュフ)ラインラントが日本の鈑金塗装工場向けに設定した資格認証(写真)を受ける工場の存在である。ここ数年、全国の車体整備工場やディーラーの車体整備部門で認証取得する事業所が増えており、2023年11月現在でプラチナ認証63、ゴールド認証111、BMW認定BP工場50が認証されている。
それは、審査を受けるまでの過程で、社員全体や部門ごとに話し合うことから始まり、実際の業務の中でPDCA(Plan→Do→Check→Action=計画→実行→確認→改善)を繰り返す。さまざまな問題点を改善することによって、社員全体の意識を向上させ、さらには生産性を高めながら、自然に作業の質と効率を高めていく手法を期待している。審査を受けて合格しても、定期的に審査を受けなければ、認証を維持できないため、普段からの継続と努力が必要とされている。
こうした自主的な取り組みを通じて、業界として技術水準を維持し、さらに向上させようと努力している。それが将来に向けた、顧客に安全・安心や地球環境保全を提供するために必要要件となっていると理解していいだろう。
11. 募集と入庫
通販会社の損保会社での営業スタイルは、インターネット経由で販売契約(募集)するため、ボディショップ側は修理サービスを担当すれば良かった。一方国内損保会社の場合は、代理店経由での販売が主であった。修理工場が代理店となって損害保険を募集するケースも多い。顧客とのつながりを継続的に持続できるからだ。もちろん修理代でも大きな収益を得られるが、代理店としての手数料収入も貴重な収益源となっている。
さて、冒頭で触れたBM社のニュースに戻してみる。店にとってみれば、顧客が直接店舗に来店する固定客を確保できることほど、メリットが多く効率的である。顧客にとってはワンストップでさまざまな手続きができる。店側は手間が省ける。自賠責の強制保険は、こうした新車・中古車購入時に店舗で加入することが多い。損害保険代理店であれば、自賠責保険や任意の車両、対人、対物保険の収入保険料が多くなれば、手数料収入は増える。顧客数が多く、かつ店舗数が多い分だけでも相当な手数料になる。
その金額の多寡によって入庫誘導が有利になるという話を、以前の勤務先での業務の中で耳にしていた。損保会社にとってみれば、それだけ手数料収入が増えれば業績が上がるだけに、その見返りとして事故車を優先的に誘導することができ、短期間で安価な修理サービスを提供できれば顧客は嬉しいはずだ。加えて、鈑金工場を保有している自社の場合、事故車修理を内製化できるので外注する手配をしなくても済むことである。しかも、品質を維持できる技術を持っている中古車販売会社にとって、とりわけメリットが多かったはずである。独立系のボディショップであれば、大規模なショップでもせいぜい数工場を持つくらい。BMのように一社で全国規模で数十の修理工場を所有している全国に販売網を持つ会社は日本に例はない。点検整備、車検に加え、中古車加修、修理単価の高い事故車修理を行い、すべてのアフターサービスを受け持つことが可能なのだ。そのような能力を持つからこそ収益を伸ばすことができ、相次いで出店した上で全国展開できるほどに成長を続けることが叶ったのだろう。
加えて、過剰なまでに修理金額を上乗せすれば、損保会社の見えないところで請求できたゆえ、BMの問題の原因にもつながったといえるだろう。それゆえにメリットは双方にとってさらに大きく、出向者を出していた損保会社にも相互に都合が良かったはずだ。
12. 社会的責任・地位という課題
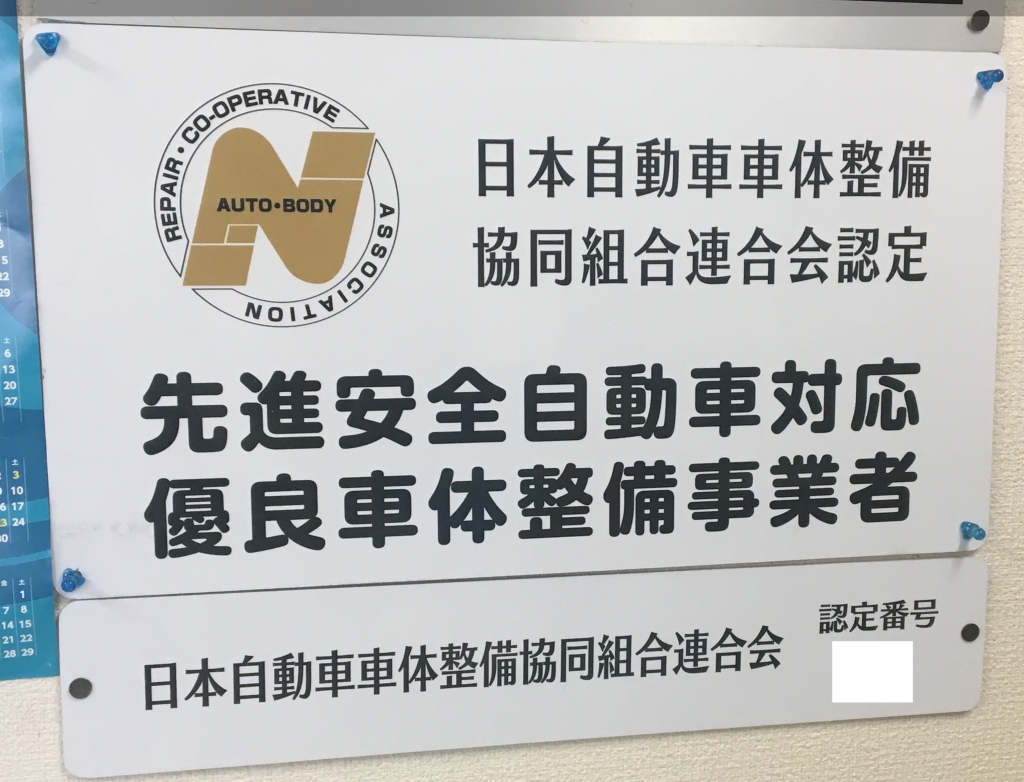
しかしBM社の一件は、道路運送車両法では整備記録簿の虚偽記載、保険業法では保険金の不正請求でそれぞれの法律に違反であるとされ、車検業務指定取消の処分がなされている。本来ならば、安全な整備サービスを提供する社会的責任を担うはずが、安全なサービスを無視した結果がこのような無責任な事件を招いたといえる。この一件で、9万軒の整備工場が長年築き上げてきた業界に対する信頼感が一挙に揺らいでしまったようにも感じる。同社が再建された際には信頼回復に努めてもらいたい。
ただ、安全な交通社会を目指すためのサービス技術は、果たしてこれまでの制度で十分なのだろうか。その課題は今後も問い続けなければならない。
これまで車体整備業界では、新しい技術が登場するたび、技術的に安全なサービスを確保するための修復作業を行う機器が必要になる。そのため常に設備投資しなければならない。こうした切なる願いから、業界側からの働きかけ、国土交通省をはじめとする監督官庁が法律の改正や新たな制度を設けるべく働きかけを行っているようだ。しかし実現には至らず、法律に基づく事故修理後の点検項目や安全を保証するための検査とはなっていない。
とはいえ新たな技術も次第に進化を続け、特定認証制度が始まっている。車体整備士の有資格者がいれば車体整備業者も工場資格を取得できるようになった。さらなる安全への対応として十分活用されることを願う。
一方、修復作業の仕上げを行うための補修用塗料はこうした法律との関連性はないものの、地球環境保全という課題を負っている。世界的に水性塗料が広く普及しているものの、日本では現時点であまり普及していない。塗料や作業全体についても社会状況によって変わっていく可能性もある。その意味では、日本だけの問題ではなく、世界における情報や状況からも判断しなければならない。
コンプライアンスと社会的課題、今は過渡期にある。今後は交通事故(特に追突事故)を起こさない車両が主流となり、鈑金・塗装でも近い将来CO2削減やサステナビリティを考慮した作業へと移り変わっていく可能性が高い。
🔷人材確保ができるのか
本論の最後にあたり、整備業界の人的資源について触れておきたい。
現在、就業前の技術教育として、自動車二級整備士を2年で養成する専門学校や短大が全国各地にある。そのような学校で構成する団体である全国自動車大学校・整備専門学校協会(JAMCA)に加盟する学校は現在47校ある。しかし近年、募集を中止したり、募集人員を減らしている。整備士養成とともに、車体整備コースを1年間で学ぶことができる専門学校や短大もあるが、やはり同様だ。かつては活況だった自動車整備士の国家資格を目指す学生がどんどん少なくなった話をしばしば耳にしている。「自動車ばなれ」という言葉も言われて久しいが、自動車業界でもとりわけメンテナンスの整備関連の仕事に携わることを好きだと思う人がいないわけではないが、その数は少なく魅力が薄らいでいる事実は否定できない。
また、報酬についても、整備士はサラリーマンと比較して平均年収で106万円の差があるというデータもある。さらに同じ整備士でも、専業工場はメーカー系ディーラーと比べ、年収ベースで108万円の差があるという。自動車整備士の給料は安いって本当?という「整備士JOBS」サイトに詳しく実態が詳しく示されているので参考にしていただきたい。
深刻な少子・高齢化時代を迎えている日本は今、どの業界でも人材不足に悩まされている印象を受ける。自動車整備業界も同じだ。専業工場はディーラーと比較しても特に条件は厳しく、給与をアップしても、すぐに辞めてなかなか定着しないなど、採用にどうしても疑心暗鬼になる。日本人スタッフを確保できないとなれば、外国人労働者あるいは技能実習生をスタッフとして雇うケースも散見する。
では、どのようにすれば人材確保の課題を克服できるのだろうか。積極的に取り組んでいる実例として、兵庫県車体協は毎年業界として広くPRする機会を開催していることを挙げたい。あるいは数年前から、国土交通省のスタッフが学生向けに業界で働く人を呼びかけようと、自動車整備士を養成する整備専門学校などに訪問したりしていたが、果たして効果は上がっているのだろうかは不明である。
ますます全国レベルで業界全体としてその魅力を積極的にアピールする機会を、各地で開くことが欠かせないだろう。別稿のドイツ・特別編にあるように、ドイツの展示会で行っていたようなPR方法は参考にしていただけたらと思う。
🔹技術教育の支援も併せて

人材確保できたとしても、業界にいかに定着してスタッフとして育成し成長させていくのか、その課題もさらに残る。
車体整備の作業は一つひとつがとても細かく、正確に技術を身につけなければならない。そのために必要なのは時間である。簡単に習得できるわけではない。しかも、自ら覚えられるものではなく、的確な指導者による訓練がなければ一人前のレベルの戦力にはなれない。以前であれば、鈑金や塗装それぞれ、月間工賃売上げで60万円ていどあげたら戦力だと言われたが、今は果たしてどうだろう。そこから、100万円とか150万円のレベルまでスキルを身につけることもでき、それが給与にも反映していった。
そのためには鈑金と塗装、それぞれ意欲や性格といった個性にあった技術を身につけることが必要だ。鈑金は叩いたり重いものを持ったり、ある程度の筋力が必要だが、損傷を受けたクルマをどの方向に戻せば修復できるのか、ベクトルなど数学的な要素が必要だという。また、塗装はスプレーガンでの塗り作業だけでなく、その前段階で調色という色合わせが必要になる。なかなか合わず根気が必要で、粘り強い性格の持ち主の方が適しているとも言われ、女性向きだという声もある。まずはどちらを好むか、意欲も大切だ。
就業後のトレーニングとしては、日本ではとりわけOJTと呼ばれる現場での訓練が一般的だが、今は鈑金であれば機械工具商社などで、塗装であれば塗料メーカーなどが行っている。アメリカやカナダの北米大陸では、I-CARが各地の研修施設で技術の習得に力を入れており、組織として施設を運営し実績を重ねている。初心者向け、中級クラス、上級者クラスなど、レベルに応じた訓練がなされ、カーメーカーの協力もあり、最新技術についても適宜対応している。I-CARはオーストラリアやニュージーランドにも広がりを見せている。ドイツでもZKFが独自で教育プログラムを行っている。日本では1994年、職業訓練法人車体修理技術振興会を設立し、滋賀県内で「ボデーリペア技術研修所」を運営していた。鈑金、塗装、見積りの基礎、中堅、応用コースなどを1週間単位で行っていたが、現在はもうない。受講者には雇用保険で研修費用が支給されるメリットもあったが、業界関係者の関心はさほど高くなく、勤務先を離れて外部に研修に出すことへの抵抗感が事業主側に強く、「技術を身につけてもどこか他に行ってしまう」といった否定的な意見も多かった。私もこの事務局を東京で担当したが、技術教育に対する壁の高さ、難しさを感じた。
そのほかに訓練施設としては、各都道府県にある職業訓練校で自動車鈑金塗装を行っている例もある。例えば、東京都立中央・城北職業能力開発センター板橋校は車体整備科があるのでウェブサイトを参考にしていただきたい。また、車体整備士の資格取得のために、各都道府県の車体整備組合が座学を開講している。
🔶今後のショップ経営は
最後に車体整備工場の経営についてである。
車体整備業者における社員の雇用形態や給与支払い方法は実は単純ではない。雇用の関係としては、社員として雇用契約を結ぶケースもあるが、どちらかといえば少数かもしれない。社員扱いではなく契約社員などでそれぞれ個人事業主となって、工場の一部スペースや設備を貸し、社内外注のように作業を請負い、それぞれの能力に見合った仕事を振り分けられるケースである。給与の支払いについても、月給の固定額での支払いもあれば、売上げの何10%を給与として支払うようにしている形態もある。契約形態をある程度のタイミングで選択できるようにしているケースがある。技術レベルに応じて仕事の質や量も、また受け取る報酬も異なり、持っている能力によって処遇が変わる世界だ。
しかし日本では、2000年前後に小キズ修理のチェーン店が業界を賑わしたことについて触れたが、結果として技術を安売りしてしまったのではないかと思う。「特急」「急行」など、どんなサービスでも時間を短縮化するならば、加算料金で割増になるのが普通だろう。しかし、営業がメインで修理内容によって価格が通常よりも安くなってしまい、結果として「サービスの安売り」になってしまった感は否めない。
つまり、一般の顧客からすれば修理料金というものがわかりにくく、加えて価格を設定する側も十分理解できていないともいえる。それだけに、適正かつ納得できるわかりやすい料金を提示できることが肝要である。まずもって、安定して従業員に対する給与を支払うことができ、かつ継続的な設備投資も可能な利益の出る経営ができるような分析やレーバーレートを基本とした価格設定が必要だ。地域の相場料金である指数対応単価を利用し、もう一度計算してみても遅くない。自社のレーバーレートの算出、その上乗せ分を認める場合もあろう。何事にも、交渉する余地が出てくるかもしれない。さらに、どのような作業のためにこれだけの見積り金額になるというその作業内容を具体的に説明すること、写真で説明する、実際に用いるツールを紹介する、作業工程を見せるなどの工夫があれば納得するだろう。

かつて訪問したボディショップでは、工場内での作業風景を見学できるスペースを設けていたところもある。説明責任とともに不安解消ができれば顧客は納得してもらえるだろう。
一方、欧米諸国では「FixAutoフィックスオート」のような世界的な車体整備のフランチャイズチェーン店がこの業界で業績を伸ばし急速にエリアを拡大している。また、世界的な流れの中では「修理権 Right to repair」という問題もあり、カーメーカーは修理工場に対して情報開示が欠かせない。日本ではメーカー系ディーラーのルートにのみ情報提供され、独立系工場には流れないという傾向が強い。しかし、こうした世界の業界でどのような流れになっているのにも事あるごとに目を向けておきたい。

日本では車検などのフランチャイズチェーンは長い歴史があり今もなお多いが、車体整備では現時点でわが国ではそのような例は見られない。それは、これまで述べてきたように日本が独自な形態で車体整備業が歴史を刻んだからだと思うので、同じ看板で集客する車体整備のチェーンが日本に上陸するとは考えにくい。
ただ、これまで述べてきたように、車体修理工場にとって集客と入庫の確保は死活問題である。これから先、事故は増加するよりも減少する可能性の方が勝っていく。かつてのような自動車を取り巻くイケイケ、バブルの時代は望むべくもない。そのような中で、将来に向けて経営基盤を固めていくことは課題だ。
損害保険会社や共済の指定工場になってある程度の入庫台数確保できる可能性があれば、経営的に安定できると考えるのも無理はない。経営資源を支えるためにいかに利益を確保できるかだ。
固定客を掴むことの難しいのが車体整備のビジネスだが、顧客と接触するポイントを増やすことがベースになるだろう。そのためには設備や人材への投資だ。自分たちが持つスキルをいかに活用できるか。可能であれば自社で行うためにスタッフへの技術教育だ。整備、磨き、エイミングなど、新たに生まれようとしている顧客をどう掴むのか。もし自分たちにスキルがなければ、互いに得意分野を融通し合えるビジネスパートナーと組むことを考えるのも一つの考え方だ。また、必要な機器類を導入するかによって、今後の経営の安定にもつながる。
そのためには高いレベルの技術、職能を持っている会社や人に対して適切な評価を与えるような仕組みが求められよう。車体整備が社会的責任のある仕事であり、その技術に対する評価と対価を、社会として認めること。そのため業界は、不断の努力を続けまだまだ課題を克服しなければならない。
<関連記事はこちらから>
自動車修理業界の現在地(I)社会的役割
自動車修理業界の現在地(II)業界の課題



[…] → 自動車修理業界の現在地(III)解決と展望 […]
いいねいいね
[…] → 自動車修理業界の現在地(Ⅲ)につづく […]
いいねいいね